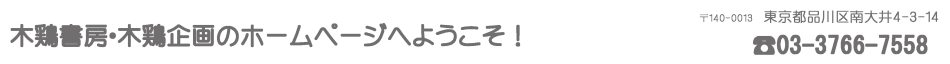商品詳細
 |
【商品名】 幻燈の街 |
●小社宛、直接ご注文の読者の皆様へ ご注文の方は、お手数をおかけしますが、封書、FAX、e-maiにてお願いいたします。 お電話での注文の受け付けはいたしませんので、くれぐれもご注意ください。 ●書店様へ 取次は(株)八木書店(03-3291-2965)をお扱い下さい。 ●メールでの注文方法 メールで住所、氏名、連絡先、注文部数をお送りください。 振込口座と送料込の金額をメールにて返信いたします。 入金確認後、2営業日以内に発送いたします。 不明な点があれば直接お問合せ下さい。 |
商品紹介 幻の蔵出し長編小説
六十余年前、梅崎春生は「丈助や仙波などと別れるの辛し。彼等に愛情を感ず」と書き残し、この言葉を最後に、人知れずこの作品をお蔵入りにした。それはなぜか?
ここに幻の長編小説を蔵から出し白日のもとにさらして、その謎の真意を問う。
本書より
(西本三十郎と会わなかったら、この俺は、九州か北海道か、どこかそんな未知の場所へ、旅に出てた筈だったんだがなあ)
茫漠たる孤独感と、旅情が、彼をおそった。彼は視線を降下させて、そこに拡がる街並みと、そこにうごめく人々の姿を見た。それらは、輝く雲の柱にくらべると、ごみごみと色褪せ、はかなく見えた。それはあたかも、幻燈に映し出された風景のように、現実感がなかった。
(こんな幻燈の街の中で、生きたり、愛したり、憎んだり、結ばれたり、離れたり、そんなことが一体何だろう?)
やがて丈助は、足をひきずりながら、のろのろと歩き出した。そんなことを考えて見たとて、人間は雲の中には住めないし、やはり人間世界に戻ってゆく他はないのだ。
書評 「毎日新聞」 (2014年7月13日)
名作「桜島」「狂い凧」「幻化」の作家、梅崎春生(1915~1965)が1952年、西日本の各紙に連載した新聞小説。単行本にならなかった。『梅崎春生全集』にも未収録という、いわば幻の作品。いまここで、梅崎春生の「新作」を読む。そんな気持ちになる。
終戦から数年後の東京。南方から復員するも、無為の日々を送る久我丈助は、自称「頼まれ屋」。たまたま知りあった初老の男・西木三十郎からは、家を飛び出した西木の妻の生活を報告するよう頼まれる。西木の娘、童話を書く男、パチンコ台の女性調律師など、さまざまな男女を見つめ、彼らと触れあうなかで、久我は徐々に人生の手ごたえらしきものを感じはじめるが、いっこうに自分の道は見えないのだ。
何のために、何を支えに生きればよいのか。「幻燈に映し出された風景のように」現実感のない日々。だが「人間世界に戻ってゆく他はないのだ」。終始ゆるやかに動く人影は、懐かしさと詩情を呼びおこす。情報の時代「以前」の人間模様を記録した作品としてみると、いっそう感興が深い。来年の梅崎春生・生誕百年を記念して刊行。
書評 「戦争と震災に共通する喪失感」 JB PRESS (2014年6月12日)
野間宏、武田泰淳らと並び第1次戦後派と言われる梅崎春生(1915~1965)の幻の長編小説『幻燈の街』が東京の小さな出版社から刊行された。
詳細はJB PRESSのページでご確認ください。
書評 六十余年の眠りから覚めた梅崎の長篇小説「幻燈の街」 岡崎幹人 (図書新聞 2014年9月6日号)
タイトルのごとく「幻」となっていた梅崎春生の長編小説「幻燈の街」が、このたび六十何年かぶりに発刊された。この小説は、一九五二(昭和二十七)年にいくつかの地方新聞に発表された作品だが、なぜか単行本にはならず、放置されたままお蔵入りにされていた。この経緯については梅崎本人が何も語っていないので、藪の中というに等しいが、それに関しては発行者でもある柳澤通博氏が、巻末の「解説・後記」で詳細に論じているので、繰り返さない。その「後記」の方に書かれているのだが、この作品をデータ化したのは何を隠そう僕自身であり、実をいうと、現在その当事者としての、責任感の一言では片付けられない、何ともいえぬ複雑な思いを噛みしめているのである。
一体全体僕は、梅崎文学の何にこれほど惹かれたのだろうか。これはいつも考えてみることだが、なぜか的確な言葉で表現することができない。梅崎の作品のすべてが、僕には無条件に面白いのは事実なのだが、その奥行きはかなりのもので、その要因をうまく説明できないのである。ただし、その理由の一つとして、梅崎文学の登場人物たちが、僕の生き方にどこか似ているというのはたしかかも知れない。梅崎文学の主人公は長篇・短篇を問わず、何というか「ケセラセラ(なるようになる)」とでもいうような、成り行き主義的なものを信条とする人物であることが多く、それは彼の小説の特徴の一つなのだが、そこが僕にはまた何ともいえないのである。
この「幻燈の街」の主人公久我丈助も、まさにその通りのケセラセラ的人物であり、戦争が終わって遅く南方から復員してきて、天涯孤独となった現実を知り、東京という場で流れるがままの生活に身を任せていたが、やがて食い詰めてしまい、どこかへあてのない旅に出ようとしていたところへ、西木三十郎という初老の紳士が関わった喧嘩に「気まぐれ」で飛び込む。それが縁となり、西木の「気まぐれ」によって東京に踏み止まることになるのだが、これまた成り行き任せに日常が流れ、最終的に丈助は、当初予定していた通りの旅に出る。この小説の妙味とは、主人公久我丈助という風変わりながらも純粋な人物を基軸にして、それに対するこれまた風変わりな登場人物たちの、当人たちは真剣なのに傍目には面白おかしいとしか見えぬやりとり、ということになるのではないだろうか。
内容はそんな他愛もない話だが、梅崎の才量が豊かなためか、とにかく最後まで一気に読ませられる。この「幻燈の街」を梅崎の他の長篇小説と比べてみると、彼の長篇小説全体の流れにおいて、重要な位置を占める作品であることは間違いない。梅崎の最初の長篇小説は「限りなき舞踏」であるが、この「幻燈の街」はそれをそっくりそのまま受けて改良した作品であるといえるだろうし、その後に続く「砂時計」はこの作品を意識して確実に方向性を変えている。
おそらく「幻燈の街」は、梅崎の長篇小説の中でも骨組みが最も露わになっている作品といえるのではあるまいか。あるいは作者の理想の構成を実現した作品といった方がよいだろうか。彼の他の作品とは少々異なり、削ぎ落とされた構成の中に(したがって登場人物も、仙波卓三のようにスッキリとわかりやすいか、西木三十郎のように徹底的にわかりにくいかだが)、主人公の意志を剥奪した分だけ彼を相手の意のままに泳がした、とでもいうような作者の構成上の意図が見えてくるはずである。
かくして梅崎本人にとっては、書き上げてみて「日記みたいな作品」となり、気恥ずかしさにあふれる作品となってしまったのだと僕は思う。それだから、愛着は十二分にあるのに、刊行はためらわれてしまったのではないだろうか。これ以後の梅崎作品には、登場人物の役割や配置がこれほど確然と割切れている作品が見られないことが、それを証明している。梅崎は以後この作品を土台にして、おそらく今日一般に知られているような彼の小説世界――要するに主人公も副人物も一癖も二癖もある者ばかり――を構築するようになる。この「幻燈の街」という作品を契機として、梅崎の長篇小説は、更なる次の段階へと見事に飛躍したのである。
ただし、一般の読者の立場に立てば、この小説はとても読みやすい作品といえるかも知れない。しかしいくら「スッキリした小説」とはいっても、梅崎の小説は一度読んでおしまいになるような薄っぺらなものでは決してなく、何度読んでもいつも何かを考えさせられるものであることだけは間違いない。いずれにしても、この「幻燈の街」は今まで梅崎小説を知らない人には、彼を読むきっかけとしてはうってつけの作品であり、また梅崎文学愛好家にとっては、今まで知らなかった梅崎小説の一部分を垣間見せてくれる稀有な作品といえるのではないだろうか。一読をお勧めする所以である。 (自然愛好家、エッセイスト)
書評 「うつろな瞳 梅崎を投影」 かごしま近代文学館学芸員 吉村弥依子 (南日本新聞 2014年10月12日号)
梅崎春生のストレートでないところが好きだ。恥ずかしがり屋、ニヒリスト、あまのじゃく。俗物と偽善が大嫌い。いつも物事を斜めに見る人。これは梅崎本人の印象であり、彼が描く主人公像でもある。
本作の主人公・久我丈助もしかり。南方での戦争体験により彼の精神はむしばまれ、復員後も社会に馴染むことができない。丈助の「深い井戸の底から、空を仰いで見たような」「空虚な放心というものを感じさせ」る目は。写真で見た梅崎自身のうつろな瞳をほうふつとさせる。
梅崎も暗号兵として赴任地の桜島で終戦を迎えたが、戦後、ノイローゼやうつ病に苦しんだ。戦争の呪縛から逃れられず、空虚な日々を過ごす元兵士の苦悩は、梅崎作品の大きなテーマのひとつとなった。かごしま近代文学館で所蔵する「幻燈の街」の創作ノートには、大きな字で「生きる意味」「生きているイミ」と書き記されている。戦後の荒廃した社会の中で、生きる意味を見いだせずにいる人々を描くことこそが本作のテーマだったのであろう。
物語は、都落ちさながら、当てのない旅に出ようとしていた職なし宿なしの丈助が、偶然出会った老紳士から、宿と「頼まれ屋」の仕事を与えられたことから始まる。混沌とした東京の町を「幻燈の街」に見立て、丈助が出会う人々の愛憎をユーモラスに描いた群像劇である。丈助は言う。「こんな幻燈の街の中で、生きたり、愛したり、憎んだり、結ばれたり、離れたり、そんなことがいったい何だろう?」。そして再び旅に出る決意をする。目的地に選んだのは…。何とも梅崎らしい選択だが、答えはぜひ作品を読んで確かめてほしい。
本作は1952年に「中国新聞」等で半年間にわたって連載されたが、生前、単行本には収録されなかった。来年の梅崎春生生誕100年・没後50年を記念して、初めて刊行されたファン待望の一冊である。来年は終戦70年の節目でもある。これを機に、他の梅崎作品も読み返してみたい。