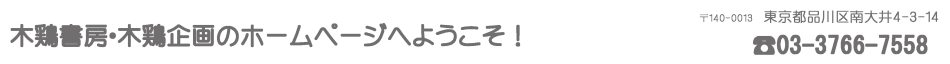商品詳細
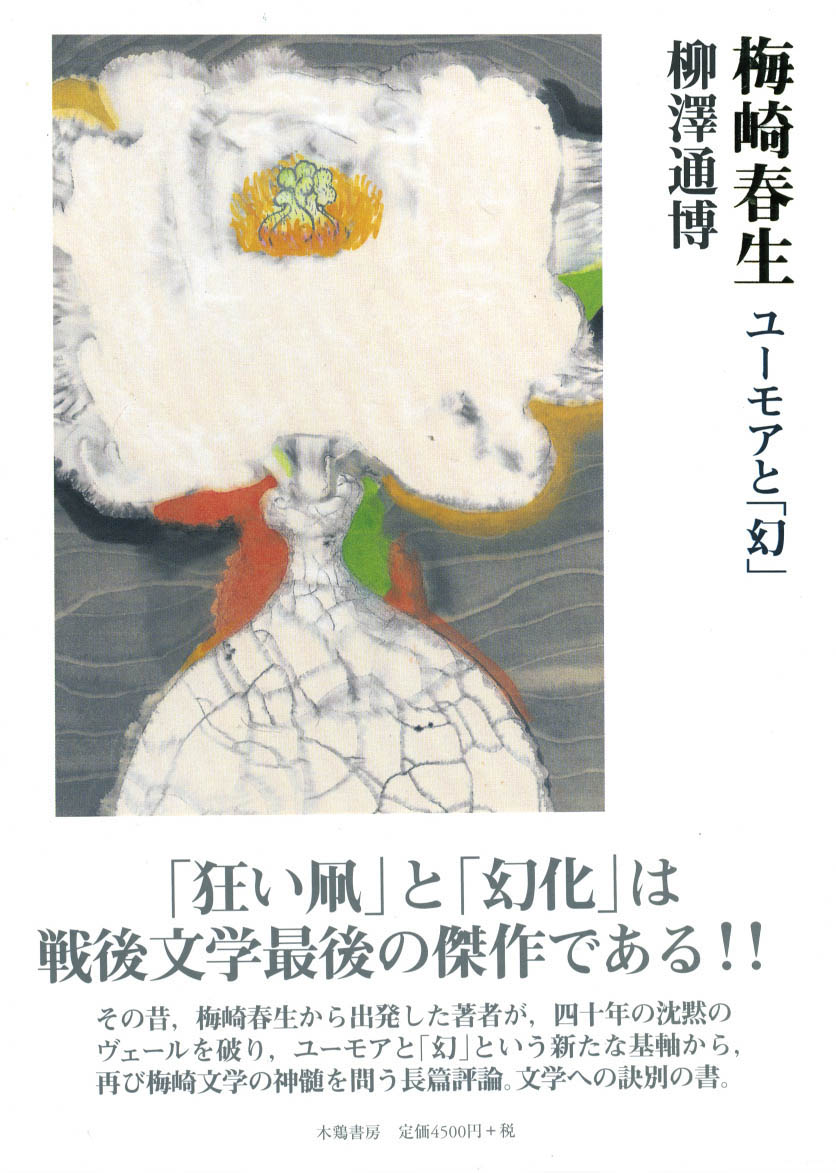 ↑クリックで画像を拡大表示することができます。 |
【商品名】 梅崎春生 ユーモアと「幻」 |
商品紹介
その昔、梅崎春生から出発した著者が、四十年の沈黙を破り、ユーモアと「幻」という新たな基軸から、再び梅崎文学の真髄を問う長篇評論。文学への訣別の書。
本書の内容
梅崎春生 ユーモアと「幻」
1 ユーモアとは何か
2 梅崎春生のユーモア
3 「陸沈」の思想
4 長編小説の問題
5 「狂い凧」
6 「幻化」
付録 初期論考
梅崎春生論
大岡昇平論
*
瓦礫の中の幻影 ――戦後文学をめぐって
喪われた「花」のありか ――志賀直哉的思考をめぐって
本書「後記より」
梅崎のことを書き残しておかねばならぬ。ある時、そんな声が聞こえたような気がした。私が「狂い凧」と「幻化」を戦後文学最後の傑作と確信しているのなら、その理由を是が非でも世に問うておかねばならぬ。それも新たに書くのなら、どうしても小林秀雄の言葉を踏まえたうえでの立論でなければ意味がない。(中略)
それから梅崎のすべての作品を丁寧に読み返し、執筆してから一年ほどかけて完成した。擱筆は今から五年ほど前だが、そのままさらしておいて上梓の思いが発酵するのを待った。異例だが、私のこの本は、その間ずっと発行を辛抱強くお待ちいただいた惠津夫人に献上したいと思う。(中略)
私の本が商売になるはずもないのはよく承知しているので、既成の版元には一切依存せず、自分で好きな本を作ることにした。部数も極少と限られているから、定価も思いのほか高価なものになってしまったが、読者諸氏には一度酒でも飲んだとお考えいただき、お許し願いたい。
書評 「図書新聞」 龍緒次郎 2011年8月13日
ユニークで素晴らしい梅崎春生論だ。久し振りに本らしい本を読んだというのが実感で、救われたような気持ちになった。何よりもまず、この梅崎論は、この著者の梅崎文学に対する熱い思いが全編に充溢しているところが好い。著者は、梅崎は彼の作品の主人公たちに変わらぬ愛情を持ち続けていたと書いているが、この著者の梅崎に対する愛情も、それに勝るとも劣らぬものだ。四十年ぶりに再論したという理由も十分に納得できる。
これまでの梅崎論は、初期の「桜島」や「日の果て」から遺作になった「幻化」に直結させてしまうような批評が多かったと記憶する。梅崎はその途中にも長短あまたのユーモア小説を書いているのだが、どちらかといえばそれは軽視される傾向にあった。文学より落語の方が詳しいというこの著者は、その間の事情を地口やネーミングに至るまで詳細な絵解きをし、晩年の「狂い凧」と「幻化」をユーモア小説の延長上の作品として位置づけてみせた。不思議な歌がいつも序曲として歌われる「酔眼」の世界というのも面白い。それには言葉を超えた説得力があり、こんな梅崎論は今まで読んだことがない。
その端緒となったのは小林秀雄の「幻化」評だと記されているが、おそらく若い頃から小林の批評を熟読してきたというこの著者には、梅崎の文学を小林の評価に価する次元にまで高めようという意図があったのではないかと思われる。それは、著者が梅崎の思想のバックボーンに、小林が語った「荘子」の「陸沈」の思想を据えたことを見てもわかる。
著者は梅崎を「陸沈者」と呼んでいる。梅崎の作品は、すべてこの「陸沈者」の視点から書かれたともいっている。「陸沈」とは耳慣れない不思議な言葉だが、この思想は中国古来の隠士・逸民の系譜をひくもので、現在の我々の意識の中にもいまだに根強く生き続けているという。著者はこの世には「陸沈者」は相当数の人たちが存在し、これからはその数をますだろうと書いているが、これには少なからず共感を覚える。目立つことだけがもてはやされるのが世の通例だが、陸に沈むことの意はもっと大切であろう。そういわれると、世の「陸沈者」諸兄にエールをおくりたい心境にもなる。
著者は、この「陸沈」とユーモアを両軸にして、論理を展開していくのだが、その圧巻はなんといっても「狂い凧」の章であろう。著者はここで彼自身の考えをすべて披露しているように見える。西洋に学んだ我々の知識は、すべて日本語という言語のもつ感性のたまものだったということ、この言語は絶対は相対だという道家の思想に準拠していること、この思想をつきつめていけば無私の精神にしか行き着かないということ、その無私は老子の「私無カラントスルハ、乃チ私ナリ」という教条を十分に踏まえねばならぬということ、それが我々日本人の特性ではないかということ、さらには、中国の古代思想が正確に継承されたのは、我々日本人だけだという注目すべき指摘まで、詳細に論じられている。
その是非について論じる資格は私にはないが、「狂い凧」というこの不可思議で難解な作品が、これほど丹念に詳細に論じられたことはこれまで一度もなかったと思う。梅崎の作品の中では、「狂い凧」は私の好きな作品の一つだが、この著者はおそらく私以上にこの作品を好きなのではないだろうか。そんなことを想像しながら読むと、この作品が「幻化」とともに「戦後文学最後の傑作である」というこの著者の評価も、十分に説得力を持つものだし、「梅崎の文学はいまだ死んではいない」という結論にも、勿論同感である。
本書には巻末に長い「後記」が記されていて、そこに著者の文学に対する思いが語られているのだが、本書はなぜか「文学への訣別の書」なのだそうである。文学とは言葉と精神の産物なのだから、人間は生きている限り文学と訣別することなどできるわけはないのだが、そんなことはこの著者にはすでに自明であろう。そう書いてみただけのことかもしれない。ここで私的に論じられている小林秀雄、遠山一行、秋山駿らからの恩恵も、中上健次や立松和平らから始まる「団塊」の世代観も、すべてなるほどと共感できるものであったが、これを読む限りでは、この著者の生き方は、若いころから一貫して固有の「陸沈者」的なものだし、これほど文学的な生き方もないのではないかと思われる。著者はどう弁明するかはしらないが、それでも文学と訣別したいというのは、いささか不可解ではないか。いずれにしても、本書からは、梅崎以外にもいろいろなことを考えさせられた。一読に価する本である。